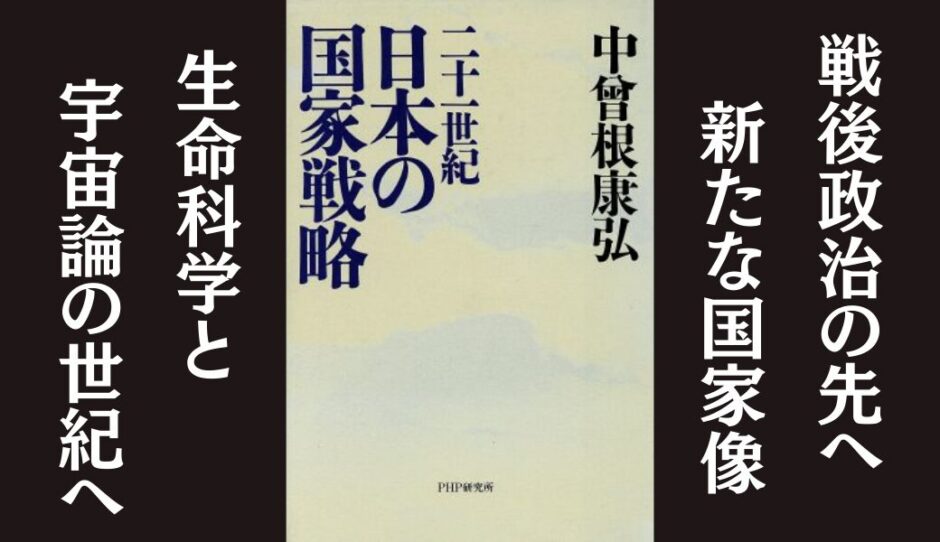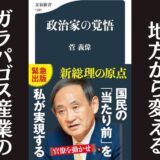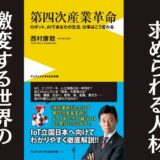中曽根康弘「二十一世紀日本の国家戦略」を読み解く
激動の時代21世紀の指南書
「二十一世紀日本の国家戦略」は、2000年に発行。
著者は、第71代内閣総理大臣を務めた中曽根康弘です。
本書は、50年以上にわたり日本の政治の中枢に携わってきた経験を基に、20世紀の総括と21世紀の日本が進むべき道を多岐にわたる分野にわたり提言しています。
20年以上前に書かれた本ですが、中曽根康弘の慧眼に驚かされました。
冷戦後の世界を読み解く鋭い視点
まず本書は、冷戦後の世界情勢を鋭く分析している点で非常に興味深い内容となっています。例えば、ソ連崩壊後の世界について、米ソの対立構造が消滅したことで、これまで抑圧されていた民族的、宗教的、経済的な対立が顕在化し、地域紛争や地域的覇権主義の台頭を招く可能性を指摘しています。
また、中国については、12億人の人口を擁する当時・世界第7位の経済大国として、近い将来、研究者数においても日本を凌駕する可能性を指摘し、その潜在的な力の大きさに警鐘を鳴らしています。
一方で、旧ソ連と同様に、共産主義体制下における集中的な資源投入によって、特定分野で世界トップクラスに躍り出る可能性にも触れ、その特徴を正しく理解した上で付き合っていく必要性を説いています。
「対話」による政治の再生を訴える
中曽根康弘は、長期にわたる政治経験の中で、国内外問わず多くの政治家と対話を重ねてきました。その経験から、政治家にとって最も重要な資質の一つとして「対話力」を挙げ、相手との信頼関係を築き、合意形成を導くことの重要性を説いています。
その具体的な例として、本書では、レーガン元大統領やゴルバチョフ元書記長とのエピソードが紹介されています。特に印象的なのは、レーガン元大統領とのエピソードです。中曽根康弘は、レーガン元大統領を「太陽のような心の温かい人」と評し、個人的な信頼関係を築けたことが、日米関係の強化に繋がったと述べています。
教育改革への熱い思い
本書で繰り返し強調されているのが、教育改革の必要性です。中曽根康弘は、戦後の教育を「国家や共同体、あるいは内部のルールを解体することに力点を置いてきた」と批判。
その結果、経済が低迷し、社会に閉塞感が蔓延していると指摘しています。
その解決策として、日本の歴史や伝統を踏まえた上で、国際社会で活躍できる人材を育成することの重要性を訴えています。具体的な改革案としては、「小学校は読み書きソロバンと躾を」という持論を展開。礎学力の充実と道徳教育の重要性を説いています。
痛烈な「臨教審」への反省
中曽根康弘は、自らの政権下で設置した臨時教育審議会(臨教審)について、その成果と限界を率直に語っています。特に、事務局の構成に文部省が多数を占めた結果、「我々が当初期待したようなものにはならなかった」と、人選の失敗を痛烈に反省しています。
その上で、今後の教育改革を進めるにあたっては、「官僚主導」では限界があることを改めて認識し、政治家、民間人、そして国民一人ひとりが当事者意識を持って取り組むべきだと訴えています。
まとめ
「二十一世紀日本の国家戦略」は、20世紀の激動の歴史を振り返りながら、21世紀の日本が進むべき道を多岐にわたって提言した意欲的な書です。
当時の政治の舞台裏や国際社会の動向、教育問題など、中曽根康弘の経験と洞察に基づいた内容は、現代社会を生きる私たちにとっても示唆に富むものばかりです。
政治家本の醍醐味の一つは、歴史の答え合わせ。
本書を今読むことで、さまざまな気づきが得られた一冊でした。
本の目次と要約
第一章 日本の国家戦略
- はじめに:二十世紀の反省と二十一世紀への構想
二十世紀から二十一世紀に移り変わる現代は、過去を反省し、未来への構想を固めるときである。混迷の時代だからこそ、国際関係の変化やIT革命などを踏まえ、日本の国家戦略を明確にする必要性を提示する。 - 日本の進路を誤らせた要因分析
フランスの政治学者、ジャック・ジュリアールの指摘を引用し、日本政治の課題として、政治的説明責任の不足、国家目標の不明確さ、政府首脳への不信などを挙げる。 - 戦略研究の必要性
冷戦後の国際情勢の変化、複雑化する国際関係、日本の国益と行動方針、長期的な国家目標設定の必要性について論じる。 - 冷戦後のアジア太平洋地域の戦略情勢展望
冷戦後の国際関係の二元構造から一元化への移行、ヨーロッパとアジア太平洋地域の安全保障環境の違い、アメリカの軍事プレゼンスと経済発展の関係などを分析する。 - 現代日本における国家戦略策定上の急所
現代日本の国家戦略策定における課題として、内閣機能の強化、情報収集体制の強化、官僚機構の改革、政権交代への対応などを挙げる。 - 日本外交の戦略目標
日本の外交戦略目標として、国連の常任理事国入り、日米同盟関係の強化、アジア太平洋地域における経済連携の強化、北朝鮮問題への対応などを提示する。 - 二十一世紀の文化戦略
二十一世紀の文化戦略として、過去の過ちの清算、良き伝統の継承、新しい創造への発展の3つを柱に据える。具体的には、科学技術の発展と精神文化の調和、日本文化の再評価、国際社会への貢献などを目指す。
第二章 二十世紀、日本の点検
- 世界史的大事件 ― 大東亜戦争とその遠因
大東亜戦争の原因とその後の世界史・日本史への影響について、冷静な分析と実証性の必要性を訴える。 - 現行憲法の曖昧さが再び禍根となる
大正時代以降の日本の政治状況、特に元老の死去による天皇の統帥権独立の意識の高まりと、国際的責任の欠如が、大東亜戦争へと繋がったと分析する。 - 戦後前期 ― 輝かしいピラミッドを築いた時代
戦後、自民党中心の政権が続いたことで、政治の安定と経済成長が実現したと評価する。鳩山一郎、岸信介、池田勇人、佐藤栄作各首相の功績を振り返る。 - 戦後後期 ― 散乱の時代、日本の混迷と衰退
戦後後期になると、政治の腐敗、ソ連崩壊による国際情勢の不安定化、バブル崩壊などにより、日本は混迷と衰退の時代を迎えたと分析する。
第三章 首相の決断 ― 大学における対話
- 総理になるための布石
中曽根が総理大臣になるまでの道のりを振り返りながら、政治家としての信念や行動力、リーダーシップについて語る。 - ディンクティブ・ポリティックス
独自の政策を打ち出す「ディンクティブ・ポリティックス」の重要性を強調し、その具体例として、日米首脳会談でのエピソードなどを紹介する。 - サミットは政治家のオリンピック
サミットを政治家のオリンピックと位置づけ、国際社会における日本のプレゼンスを高めることの重要性を説く。 - 行政改革の「工程管理表」
行政改革を進めるにあたっては、具体的な目標設定や工程管理表の作成が不可欠であると主張する。
第四章 二十一世紀、日本の展望と国策
- 国家の再定義
グローバリゼーションの進展により、国家のあり方が問われていると指摘し、その上で、日本は国際社会において積極的な役割を果たしていくべきだと主張する。 - 世界五大潮流の調整
インダストリアリゼーション、デモクラタイゼーション、ナショナリズム、リージョナリズム、グローバリゼーションという世界五大潮流を、日本はどのように調整していくべきかを論じる。 - 自白の合流と保守二大政党制
日本の政治状況を分析し、自民党と民主党による二大政党制の必要性を訴える。
第五章 日本の経済戦略
- 構造改革なくして成長なし
日本経済の現状を分析し、構造改革の必要性を訴える。特に、財政再建、金融システム改革、規制緩和などを重点課題として挙げる。 - 財政再建の基本構想
財政再建の目標、具体策、工程管理表を定める「財政再建基本法」の制定を提言する。 - 日本経済再生のための緊急提言
日本経済再生のために、政府、企業、個人がそれぞれ取り組むべき課題を提示する。
第六章 国民憲法制定論
- 自主独立の国家を目指して
敗戦後、アメリカの占領下で制定された日本国憲法について、その歴史的背景を踏まえながら、自主独立の国家としてのあり方を論じる。 - 吉田外交と憲法改正
吉田茂首相の外交政策を評価しつつも、憲法改正については消極的であったと指摘する。 - かつての憲法調査会の真相
1956年に発足した憲法調査会での議論を振り返りながら、憲法改正をめぐる当時の状況を解説する。 - 前文、第九条、その他の問題点
現行憲法の問題点として、前文、第九条、教育基本法、人権と義務のバランス、首相公選制などを挙げる。 - 自衛隊違憲論の誤り
自衛隊違憲論は誤りであると断言し、自衛隊の必要性と憲法との整合性を主張する。 - 集団的自衛権行使の容認
集団的自衛権の行使を容認し、そのための法整備の必要性を訴える。 - 首相公選制導入の必要性
首相公選制を導入することで、政治のリーダーシップと責任体制を明確化できると主張する。
第七章 日本の教育改革
- 混迷する教育界への緊急提言
日本の教育界の混迷を憂い、抜本的な改革の必要性を訴える。 - 「創造的破壊」の改革
グローバリゼーションとナショナリズムのバランスを取りながら、「創造的破壊」による教育改革を提言する。 - 日本全体の文明病
日本の教育問題を「文明病」と位置づけ、その根本的な原因を分析する。 - 蒸留水を蒸留する教育
日本の教育は、知識偏重で、思考力や創造性を育む視点が欠けていると指摘する。 - 急所を衝いた答申になっていない
過去の教育改革の提言は、抽象的な議論が多く、具体的な改革案が欠落していると批判する。 - 他との関わりで創られる自己
個人の確立のためには、他者との関係性の中で自己を形成していくことが重要だと指摘する。 - 独創性教育には陥穽がある
独創性を重視するあまり、基礎学力がおろそかになっている現状を批判する。 - イベント化する文化政策
日本の文化政策は、イベント重視で、長期的な視点が欠けていると指摘する。 - 小学校は読み書きソロバンと躾を
小学校教育では、基礎学力の習得と、規範意識や道徳心を育むことが重要だと主張する。 - 適材適所ができない人材登用
大学などにおける人材登用において、適材適所が実現していない現状を批判する。
第八章 日本の科学技術政策
- 二十世紀、科学技術の展開
二十世紀の科学技術の進歩を振り返りながら、その光と影を分析する。 - 二十一世紀、国家と科学技術
二十一世紀における科学技術政策のあり方について、国際競争の激化、科学技術と社会との関係、倫理的な課題などを踏まえて論じる。 - 戦後、日本の科学技術政策の展開
戦後の日本の科学技術政策を振り返りながら、その成果と課題を分析する。 - 社会とともに進む科学技術
科学技術は社会と調和しながら発展していくべきだと主張する。 - わが国の研究開発システムの改革
日本の研究開発システムの課題を指摘し、その改革の方向性を提示する。 - 科学技術政策 ― 三つの創造的破壊
科学技術政策において、「創造的破壊」が必要な3つの分野として、研究開発システム、人材育成、国際協力 を挙げる。 - 指導者の自覚
科学技術政策を推進していくためには、指導者の明確なビジョンとリーダーシップが不可欠であると訴える。 - 新開発科学技術体系の確立
新しい時代に対応した科学技術体系を確立する必要性を訴える。 - ヒト・ゲノムの解読を終えて
ヒトゲノム計画の完了を踏まえ、生命倫理、遺伝子治療、個別化医療など、今後の課題を展望する。 - 日本における二十一世紀科学技術の重要な開発
二十一世紀の日本にとって重要な科学技術開発として、脳科学、ナノテクノロジー、環境技術、情報通信技術などを挙げる。 - 思想哲学の確立の必要
科学技術の発展は、倫理的な問題や社会への影響など、様々な課題を提起していると指摘し、その上で、新しい時代に対応した思想や哲学を確立する必要性を訴える。