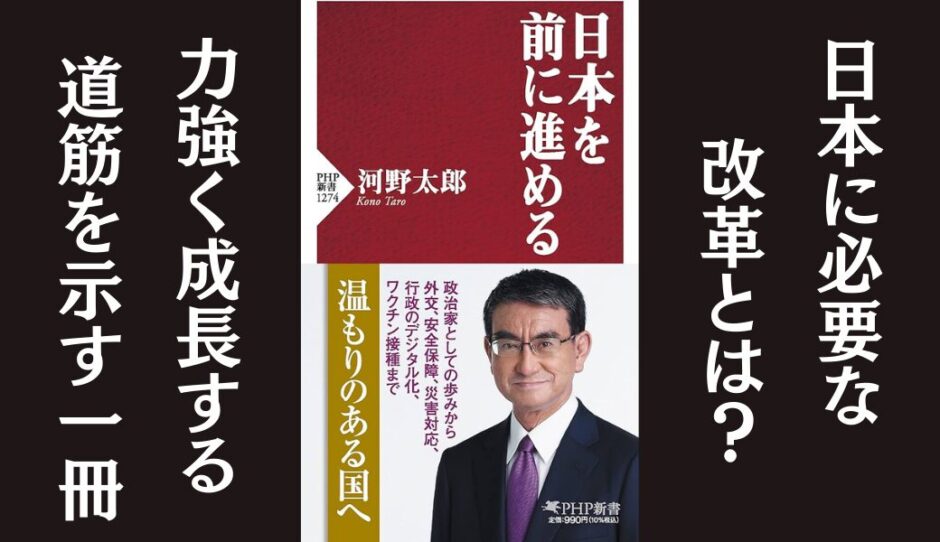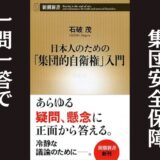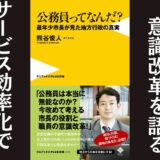河野太郎の原点と未来への展望
2021年に発行された「日本を前に進める」は、河野太郎氏が自身の半生を振り返りつつ、日本が直面する様々な課題に対する具体的な政策提言を行った一冊です。政治家・河野太郎の原点から、外交、防災、エネルギー、社会保障、教育、デジタル化といった幅広いテーマについて、氏の経験に基づいた提言が展開されています。
幼少期の迷子事件に見る行動力
本書の魅力は、何と言っても河野氏の率直な人柄が伝わってくるエピソードの数々です。例えば、第一章では、小学校1年生の時に家族で出かけた際に迷子になった経験が紹介されています。
親に叱られたことが原因で汽車に乗り遅れてしまった河野少年は、一人で電車に乗って平塚の自宅を目指します。この時、わずか6歳の少年が行動したというエピソードからは、後に政治家として活躍する河野氏の片鱗を垣間見ることができます。
若き日のワレサ議長との遭遇
また、ジョージタウン大学在学中にポーランドの民主化運動のリーダーであったワレサ議長に会うため、単身ポーランドへ渡ったエピソードも印象的です。当時、共産主義体制下にあったポーランドでは、反政府活動は厳しく取り締まられており、ワレサ議長自身も自宅軟禁の状態にありました。
河野氏は、現地の学生から教えられた教会で偶然を装ってワレサ議長と面会し、民主化運動に対する支持を表明しています。その後、警官に身柄を拘束されるという波乱もありましたが、この経験を通して、自由と民主主義の尊さを改めて実感したと述べています。
政治家としての河野太郎
その後、1996年、43歳の時に衆議院議員に初当選してからの活動についても、本書では詳しく紹介されています。特に、消費者問題、外交、防災、エネルギー問題など、多岐にわたる分野で辣腕を振るってきた河野氏の実績は目を見張るものがあります。
例えば、消費者問題担当大臣として、遺伝子組み換え食品の表示義務化に尽力したエピソードは、氏の信念である「国民の知る権利」を強く意識した行動として紹介されています。また、外務大臣時代には、年間100日を超える海外出張をこなし、地球儀を飛び回るように各国首脳と会談を重ねるなど、精力的な外交活動を行ってきました。
河野太郎が描く未来への提言
本書では、こうした経験を踏まえ、今後の日本が進むべき方向性についても具体的な提言がなされています。
- 少子高齢化が進む日本において、持続可能な社会保障制度の構築は喫緊の課題です。河野氏は、国民一人ひとりが自分のライフプランに応じて自助努力で老後の生活資金を準備できるよう、積立方式の年金制度への移行を提案しています。
- また、グローバル化が加速する中、日本が国際社会でリーダーシップを発揮していくためには、英語教育の抜本的な改革が不可欠であると主張しています。
- さらに、AIやIoTなどの技術革新を最大限に活用し、国民生活の利便性を向上させると同時に、経済成長につなげていく「デジタル化」の重要性についても強調しています。
まとめ
「日本を前に進める」は、河野太郎という政治家の信念や行動原理を知る上で必読の書と言えるでしょう。 特に、日本が遅れているデジタル化については、興味深く読めると思います。
本の目次と要約
第一章 政治家・河野太郎の原点
- 迷子の思い出: 幼少期の著者のある出来事を通して、当時の家族の様子や自身の性格を振り返る。
- 箱根駅伝を目指して: 慶應義塾中等部から大学まで、青春時代を陸上競技に捧げた経験について述べている。
- アメリカ留学: 大学時代に希望していたアメリカ留学を実現させるまでの経緯、留学先での経験について触れている。
- レーガン選挙のボランティア: アメリカ留学中にレーガン大統領選挙のボランティア活動に参加した経験、当時の政治への関心の高まりについて述べている。
- ポーランドで連行される: 冷戦下のポーランドで民主化運動に関わったことで当局に連行された経験を通して、当時の社会状況や自身の行動力について振り返る。
- 富士通へ就職: 帰国後、富士通への就職を決意するまでの背景、政治家になるという選択肢がまだ見えていなかったことを述べている。
- サッチャーとの出会い: 富士通時代に経験したサッチャー首相との出会いが、その後の政治家としての活動に影響を与えたことを述べている。
- 政治家への道: 政治家になることを決意した背景、当時の政治状況や周囲の人々の後押しについて述べている。
- 初当選: 初当選を果たすまでの選挙活動の様子、家族の支えについて触れている。
- 父の病気: 父親である河野洋平氏のC型肝炎発覚から闘病生活について、当時の心境を交えながら述べている。
- ドナーになる決心: 父親への生体肝移植を決意するまでの葛藤、家族との話し合いについて触れている。
- 手術: 父親への生体肝移植手術の様子、その後の経過について詳しく述べている。
- 生体肝移植をめぐって: 自身の経験を通して、生体肝移植に対する考え方や臓器移植法改正への取り組みについて述べている。
第二章 父と私
- 生体肝移植をめぐって: 前章から続く、生体肝移植についての自身の考えや社会への問題提起、臓器移植法改正への取り組みについて詳しく述べている。
第三章 新しい国際秩序にどう対処するのか ― 安全保障・外交戦略
- 激動する世界: 日本を取り巻く国際情勢の変化、中国の台頭とアメリカの影響力低下について分析している。
- これからの安全保障の枠組み: 新しい国際秩序における日本の安全保障政策、日米同盟の重要性と多国間協力の必要性について述べている。
- 【外交】: ポストコロナ時代における日本の外交戦略、自由と民主主義、人権の尊重などを基軸とした国際秩序への貢献について述べている。
- 外交を進める体制: 日本の外交力を強化するために必要な外交官の増員や待遇改善、外務省の組織改革について述べている。
- 外務大臣に外交を: 外務大臣時代の経験を踏まえ、日本の外交における課題や改善点について具体的な提案を行っている。
- 何のためのODAか: 日本の政府開発援助 (ODA) の意義や役割、効果的な活用方法について、具体的な事例を交えながら解説している。
- アジアの民主主義: アジア諸国の民主化運動に対する日本の役割、欧米諸国との違いを明確にしながら、人権問題への取り組み方について述べている。
- 中東外交: 中東地域における日本の外交戦略、イスラエル・パレスチナ問題への取り組み、アラブ諸国との関係強化について述べている。
第四章 防災4.0
- 防災の司令塔はいかにあるべきか: 日本の防災行政の課題、内閣府の役割強化や専門人材の育成、縦割り行政の弊害について述べている。
- 防災4・0で災害の激甚化に備えよう: 過去の災害の教訓を踏まえ、近年の災害の激甚化に対応するための新しい防災の考え方「防災4.0」について提唱している。
- 新しい復旧のあり方: 従来の原形復旧だけでなく、創造的な復興を推進する必要性、防災事業における課題や土地収用法の改正について述べている。
- 感染症対策: 新型コロナウイルス感染症の教訓を踏まえ、今後の感染症対策における政府の役割、ワクチン開発や医療体制の強化について述べている。
第五章 エネルギー革命を起爆剤に
- 政府の中で: 政府のエネルギー政策における課題、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取り組みや原子力政策の見直しについて述べている。
- 消費者問題として: 電力自由化における消費者保護の重要性、電力会社の不適切な販売方法や契約内容の問題点、行政の対応について述べている。
- 行政改革の一環として: 行政改革担当大臣時代の経験を踏まえ、エネルギー・原子力分野における行政改革の必要性、具体的な改革内容について述べている。
- 日本の再生可能エネルギー外交を宣言: 外務大臣として、世界に向けて日本の再生可能エネルギー導入に向けた決意表明、国際協力の重要性について述べている。
- 気候変動に関する有識者会合: 気候変動問題に対する日本の取り組み、外務省の有識者会合での提言内容、再生可能エネルギーの導入目標について解説している。
- 再生可能エネルギーと安全保障: 再生可能エネルギー導入の安全保障上のメリット、自衛隊の取り組みなどを事例に挙げながら、エネルギー安全保障の重要性について述べている。
- 規制改革: 再生可能エネルギー導入を阻害する規制の課題、電力系統の運用ルールの見直しや送電網の増強など、具体的な改革案について提言している。
- 言われない批判: 原子力政策に関する批判に対して、具体的なデータや事実を基に反論、エネルギー政策のtransparencyの重要性について述べている。
第六章 国民にわかる社会保障
- 構造上の問題: 日本の社会保障制度の構造的な問題点、高齢化と少子化による財政負担の増大、社会保険制度の複雑さについて解説している。
- 国民にわかる社会保障: 社会保障制度改革の必要性、国民一人ひとりが制度を理解し、議論に参加できるよう、わかりやすい情報提供の重要性を訴えている。
第七章 必要とされる教育を
- 教育のICT化: オンライン教育の活用、教育現場におけるICT導入の現状と課題、デジタルデバイドの解消、教師のICT活用スキル向上などについて述べている。
- 習熟度別の教育の充実: すべての子供が個性や能力を最大限に伸ばせるよう、習熟度別の教育の必要性、少人数教育や個別指導の充実、ICTの活用について述べている。
- 子どもの貧困をなくす: 子供の貧困問題の現状と課題、経済状況による教育格差の解消、就学援助制度の拡充、学習支援や生活支援の必要性について述べている。
第八章 温もりを大切にするデジタル化
- デジタル化で温かく信頼される政治を: デジタル化を推進することで、行政サービスの向上や国民生活の利便性向上を図るとともに、人々のつながりや温かさを重視した社会の実現を目指すべきだと述べている。
- シンガポールに学ぶこと: シンガポールにおけるデジタル化の先進事例を紹介し、日本が学ぶべき点として、国民IDの活用や行政手続きのオンライン化、国民へのデジタルリテラシー教育などを挙げている。
- データの共有: データ共有による社会課題解決の可能性と課題、個人情報保護とのバランス、政府・企業・個人のそれぞれが担うべき役割について述べている。
- デジタル再分配も重要に: デジタル化による恩恵を社会全体に公平に行き渡らせる「デジタル再分配」の重要性、そのための具体的な政策として、デジタルインフラ整備やデジタルスキル教育、低所得者への支援などを挙げている。
- デジタル時代の人への投資: デジタル時代に求められる人材育成、リカレント教育の重要性、リスキリングの促進、成長分野への投資などについて述べている。
- 地方経済の活性化: デジタル化による地方経済活性化の可能性、リモートワークの普及、地方の魅力発信、デジタル人材の育成などについて述べている。
おわりに: 本書の締めくくりとして、著者の政治に対する思い、国民一人ひとりが政治に参加することの重要性、日本の未来に対する希望を語っている。