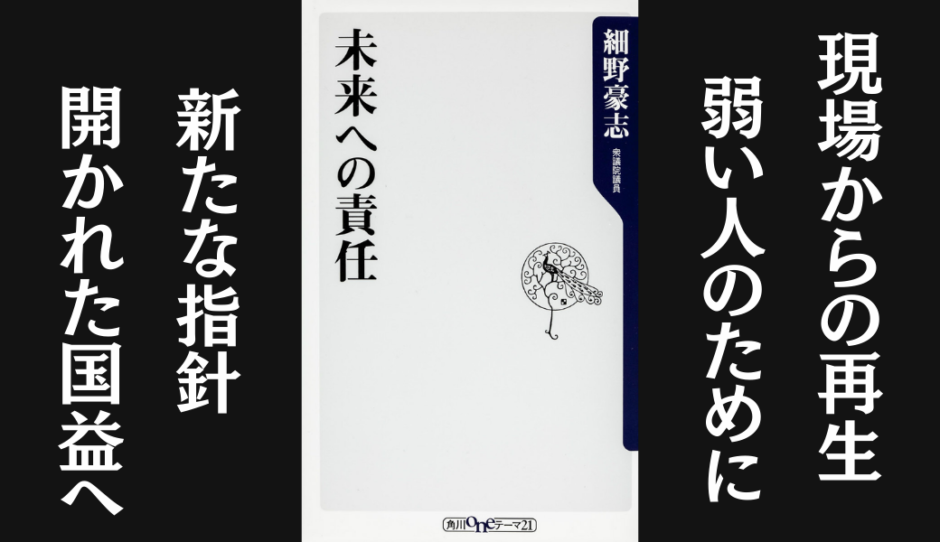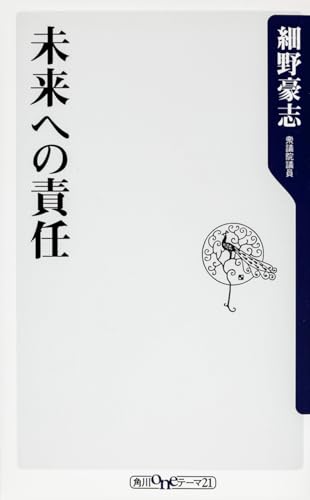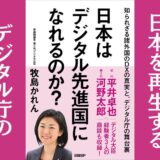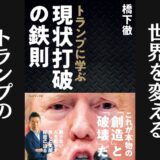政治の責任を問う、細野豪志の覚悟とは? ― 民主党再生への道筋を示した「未来への責任」
2013年6月に出版された「未来への責任」は、民主党政権で中心的な役割を担った細野豪志氏による、民主党政権の回顧と今後の日本社会への提言をまとめた一冊です。本書では、細野氏が経験した政治の現場での生々しいエピソードや、民主党政権誕生から崩壊、そして野党転落に至るまでの政治のダイナミズムが赤裸々に描かれています。特に、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の対応における、政治家としての葛藤と決断は、読者に深い感銘を与えます。
民主党政権は何を目指したのか? ― チルドレンファースト、社会保障、そして地域主権
細野氏は、民主党政権が目指した3つの柱として、「チルドレンファースト」「年金をはじめとした社会保障と税の一体改革」「地域主権」を挙げ、その具体的な政策内容を紹介しています。
「チルドレンファースト」では、子育て支援の充実を図るために、小児科や産婦人科の医療報酬を引き上げ、現場の待遇改善を目指したと述べています。医療費全体が膨らんでしまうという懸念もありましたが、医療を受ける国民の立場に立って行動したと、当時の決断を振り返っています。
「社会保障と税の一体改革」については、自民党との根本的な認識の違いを指摘しています。自民党の一部には社会保障は経済の負担であるという認識がある一方で、細野氏は社会保障の充実が国民の安心につながり、経済成長にプラスになると考えています。年金問題を例に挙げ、少子高齢化が進む中で現行の年金制度が制度疲労を起こしていることを数字を交えながら説明し、抜本的な改革の必要性を訴えています。
「地域主権」の実現に向けては、地方分権の推進と地域経済の活性化に力を入れたことを強調しています。特に、リーマンショック後の経済状況下においても、地道な政策を積み重ねることで、有効求人倍率や完全失業率の改善、倒産件数の減少といった成果が表れたことを具体的に示しています。
福島の人々へ、私が果たすべき責任 ― 未曾有の原発事故に政治はどう向き合ったのか
細野氏は、東日本大震災発生後、未曾有の原発事故に直面し、原子力発電所事故収束・再発防止担当大臣、内閣府特命担当大臣(原子力行政)、環境大臣を歴任しました。本書では、事故対応の最前線に立ち続けた経験から、当時の状況や自身の葛藤、そして教訓を語っています。
特に印象的なのは、事故発生当初、最悪のシナリオを想定して行動することの重要性を訴えたエピソードです。当時は楽観論が蔓延し、事後的な対応に追われる状況でしたが、細野氏は「最悪のさらに最悪」を想定したシナリオ作成を指示し、政府としてあらゆる事態に備えるべきだと主張しました。この時の経験から、政治家は時に国民を危険な場所に送り込む決断を迫られること、そしてその責任の重さを痛感したと述べています。
また、ガレキ処理問題では、放射能への不安から広域処理が難航する中、安全性を丁寧に説明し、各自治体に理解を求める活動を行いました。その中で、静岡県島田市長のリーダーシップと住民の理解によって、広域処理が実現したことに深く感謝の意を表しています。
共に生きる社会を築くために ― 政治家・細野豪志の信念
細野氏は、民主党が目指すべき社会として「共に生きる社会」を掲げ、その実現に向けた具体的な政策を提言しています。特に、「世襲政治、企業団体献金との決別」「政治は弱い人のためにある」「新たな価値を生む土発経済の活性化」「開かれた国益を実現する」「平時は穏やかな政治、有事は大きな政治」という5つの綱領を提示し、その実現に強い意欲を示しています。
「政治は弱い人のためにある」という信念のもと、細野氏は自らの原点を振り返りながら、誰もが人生の浮き沈みを経験し、支え合って生きていることを強調しています。そして、自民党の「自助・共助・公助」という考え方に対して、真の「共に生きる社会」は、困っている人を支える仕組みを積極的に作り出すことだと主張しています。
政治に希望を託せるか? ― 読後感と読者へのメッセージ
本書は、民主党政権の功罪や東日本大震災への対応など、日本の政治の転換点となった出来事を、当事者である細野氏の視点から読み解くことができる貴重な記録です。細野氏の率直な言葉からは、政治家としての責任感と日本社会への熱い想いが伝わってきます。
一方で、民主党政権の政策の成果や課題については、本書では紙幅の制限もあり、十分に検証されているとは言えません。例えば、チルドレンファーストや社会保障制度改革など、具体的な政策の効果や影響については、更なる検証が必要だと感じました。
本書は、政治に興味関心のある方はもちろんのこと、これからの日本社会を担う若い世代にこそ読んでほしい一冊です。
本の目次と要約
はじめに
「振気」の精神、すなわち「震えるくらいの気合いでやれば、できないことは何もない。必ず道は開ける」という言葉を胸に、政治家として、そして原発事故担当大臣として、困難な状況に立ち向かってきた日々を振り返る。震災からの復興、日本の未来のために、自身の経験とそこから得た教訓を語る。
第一章 今、なぜ民主党か
敗北からの再出発
2012年末の総選挙での大敗を受けて、民主党は反省すべき点を反省し、国民の声に耳を傾け、党の再生を果たさなければならない。そのためには、過去の政策の成果と反省点を明確化し、自民党政権との違いを明確に示す必要がある。
国家主義と対峙し、民が主役の政治を実現する
自民党政権下での国家主義的な風潮に対抗し、国民が政治の主人公であるという原点に立ち返る。そのために、政治の透明性を高め、国民の声を政治に反映させる仕組み作りを進める。
民主主義を正しく機能させる
小沢一郎氏をめぐる政治と司法の問題を通して、検察審査会や裁判員制度の問題点を指摘する。メディアの報道姿勢にも疑問を呈し、民主主義社会における司法と報道のあり方を問う。
政治には人材が不可欠
民主党政権の経験を通して、政治には行政経験豊富な人材が必要であることを痛感した。優秀な人材を育成し、政権運営を担えるような体制を構築することが急務である。
海江田万里代表の覚悟
海江田万里代表は、原発事故の対応において、自らを犠牲にして職務に当たってきた。その経験と覚悟を共有し、党の再生に共に取り組む決意を示す。
前原誠司氏の行動力と決断力
前原誠司氏は、行動力と決断力に優れた政治家である。民主党政権での経験を踏まえ、今後の政治における役割に期待を寄せる。
菅直人氏と小沢一郎氏を乗り越える
菅直人氏と小沢一郎氏の確執は、民主党政権の大きな影を落とした。二人の政治手法を比較分析し、今後の民主党のあり方を考える。
民主党政権の目指したもの
チルドレンファースト
自民党政権下での社会保障費削減により、医療現場は疲弊し、子どもを持つことに不安を感じる人々が増えていた。民主党政権は、子ども手当の支給、医療費負担の軽減など、子どもを産み育てやすい社会の実現を目指した。
年金をはじめとした社会保障と税の一体改革
高齢化社会の進展に伴い、社会保障費の増大は避けられない。民主党政権は、消費税増税を含む、社会保障と税の一体改革に取り組んだ。
地域主権を実現するために
中央集権体制を改め、地方分権を進めることは、民主党政権の重要政策の一つであった。地域主権改革の成果と課題を検証し、今後の地方分権のあり方を考える。
民主党が失敗した理由
民主党政権は、様々な政策課題に取り組んだものの、国民の期待に応えられず、政権を離れることになった。その理由を分析し、今後の教訓とする。
民主党の足腰
落下傘候補(パラシュウター)
最大の試練を乗り越える
選挙が政治家を育てる
議員を支える全国のネットワーク
野党として国民の声に耳を傾ける
ハンセン病と肝炎問題から学んだこと
総理の資格
第二章 共に生きる社会をつくる
民主党新世代五綱
民主党は、国民の負託に応えるため、新世代五綱を策定した。新世代五綱は、民主党の目指す社会像と、それを実現するための具体的な政策を明らかにしたものである。
一、世襲政治、企業団体献金と決別する
二、政治は弱い人のためにある
三、新たな価値を生む土発経済の活性化
四、開かれた国益を実現する
五、平時は穏やかな政治 有事は大きな政治
綱領はなぜ必要か
民主党が大事にする価値とは
政治家の出自を越えて
保守とは何か
共に生きる社会
経済成長は誰のためか
再び、地域から
第三章 原発事故担当大臣・環境大臣として
福島の人たちへ、私が果たすべき責任
原発事故担当大臣として、そして一人の政治家として、福島の人々のために何ができるのか、何をすべきなのかを問い続ける。
最悪のシナリオ
原発事故発生当初、最悪の事態を想定したシナリオを作成し、最悪の事態に備えた。その時の緊迫した状況を振り返り、教訓を語る。
現場の作業員の頑張り
収束宣言は早すぎた
真の専門家は火中の栗を拾う
「ホソノ・プロセス」
自分の地元だと思って職務に当たる
日本全国の力が結集したガレキ処理
低線量被ばく問題
帰村宣言をした川内村
大飯原発再稼働の検証
エネルギー政策はいかにあるべきか
最も有力な地熱発電
可能性豊かな洋上風力発電
国家の責任で人材育成を
おわりに