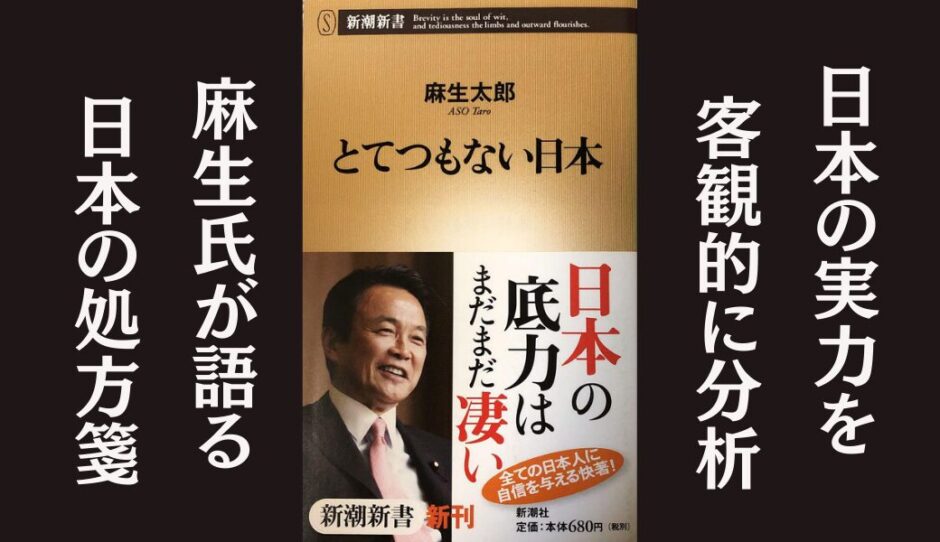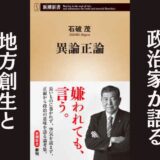冷静な視点で「日本の底力」を見つめなおそう。
麻生太郎氏の著書「とてつもない日本」(2007年 出版)を読みました。
第三次小泉改造内閣、安倍内閣と続けて外務大臣を務めた麻生氏は、
各国要人と話すことで「日本の位置づけ・実力」を冷静な視点で再確認できたと語ります。
残念なことに、日本のメディアでは「駄目な日本」が強調されて、お先真っ暗なように見えます。
格差社会・少子高齢化・教育崩壊などのネガティブなニュースが、のべつまくなし報道され、
識者やコメンテーターも「日本はなぜこんなにおかしくなったのか」と悲観的なコメントを繰り返しています。
このような「自虐的で卑下しすぎな見方」に、麻生氏は異を唱えます。
「実は、日本人が考えている以上に、日本は諸外国から評価されている」というのです。
日本流がグローバル・スタンダードである

本の中では、外国から評価されている例が紹介されています。
たとえば、
・トヨタをはじめとする自動車企業
・ソニーなどのテクノロジー企業
・任天堂などのゲーム企業
・マンガ、アニメなどのエンターテインメント
・インスタントラーメンなどの食品産業
・治安もよく、清潔な街中
などが挙げられています。
さらに、日本には魅力的な観光スポットも全国にあります。
私は、渋谷のドン・キホーテや、Nintendo TOKYOが好きでよく行くのですが、目を輝かせている興奮している外国人観光客をたくさん見かけます。
「日本はグローバル・スタンダードを導入すべし」と主張する日本の識者もいる中で、
「むしろ、日本流がグローバルスタンダードになっている」と麻生氏は語ります。
外務大臣を務め、各国からの言葉を直背聞いている麻生さんの文章には説得力がありました。
まれにみる経済的な繁栄を実現し、世界中に影響を与えている日本。
本書の中で麻生氏は、日本の特徴を3つ挙げています。
日本の特長1:成功も失敗もさらけ出す「ソート・リーダー」である

日本の強み・特徴のひとつめは、
成功も失敗もさらけ出す「ソート・リーダー」である
です。
「ソート・リーダー」の綴りは「Thought Leader」で、先駆的存在を意味します。
麻生氏は「日本は、多くの失敗を経験し、課題解決に取り組んできた」と説きます。
「諸外国より先に失敗している」のが重要なところで、本の中では2つの失敗が書かれていました。
・ナショナリズムの過剰な高ぶりから韓国や中国をはじめとする無辜の民を苦しめた
・高度成長と引き換えに、公害に代表される環境破壊を引き起こした
これは確かにうなずけるところで、日本は外国よりも先に危機や失敗が訪れている気がします。
「バブル崩壊からの不良債権問題」や、「地震大国ならではの災害」などもあるとと個人的には感じました。
そして、麻生氏が注目する最も難しい課題は「少子高齢化」です。
現在直面しているこの難問を、諸外国よりも先に解決まで導かなくてはならないと麻生氏はいいます。
たしかに、韓国や中国はもちろん、先進国の多くが「少子化の問題」を抱えています。
そのなかでも日本は、最も早く老齢化が訪れるため「どのようにこの課題を解決するか?」
日本の行動に多くの国が注目していると麻生氏は語り、かなり踏み込んだ処方箋を記しています。
この内容は、後ほど触れます。
日本の特長2:アジアにおける安定勢力「ビルトイン・スタビライザー」である

日本の強み・特長のふたつめは、
アジアにおける安定勢力「ビルトイン・スタビライザー」である
です。
「ビルトイン・スタビライザー」は、自動安定化装置を意味し、ここではアジアの平和と安定を指しています。
このアジアの平和と安定をもたらしているのはなにか?
それは、「経済」と「安全保障」だと麻生氏は説きます。
経済面では、「支援金・政府開発援助(ODA)」があります。
1997年に発生したアジア通貨危機の際には、日本は自身も不況下にあったにもかかわらず、韓国、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンなどに合計300億ドルも支援の手を差し伸べ、アジア諸国の窮地を救いました。
この強い経済が、日本のみならずアジアの平和と安定をもたらしているというのです。
また、安全保障面では、「強固な日米同盟」があります。
アメリカが軍事力を展開できる場を、日本国内に基地として提供することで、アジアの平和が保たれていると麻生氏は考えています。
日本の特長3:諸外国と対等な「ピア・ツー・ピア」関係を構築している

日本の強み・特長の3つめは、
諸外国と対等な「ピア・ツー・ピア」関係を構築している
です。
「ピア・ツー・ピア」は、コンピュータ用語で、サーバを介さずに直接データのやり取りを行うことです。
この本の中では、上下関係のある外交ではなく、対等な外交という意味で使われています。
政府開発援助(ODA)であれば、援助対象国と同じ目線で手を取り合って歩む姿勢が大事であり、
文化交流を促進するため、中国・韓国・ASEAN諸国との青年交流を強化すべきと麻生氏は語ります。
本の中では触れられていませんが、日本のパスポートは、世界で最も強力なパスポートにランクインされています。
日本は194の国・地域にビザなしで入国できるのは、日本が多くの国と良い関係を築けている証かもしれないと感じました。
「若者の雇用問題」に対する麻生氏の考え方

「第一章 アジアの実践的先駆者」では、日本は捨てたもんじゃないと熱く語る麻生氏。
「第二章 日本の底力」以降の章では、日本の国内問題に言及しています。
本の中で、最初に取り上げているのは、「若者の雇用問題」でした。
ちょっと意外だったのですが、麻生氏はニートに理解を示しています。
「すべての人が仕事での自己実現をすべきだ」という極端な理想論が、世の中に失意と落胆を満ち溢れさせてしまっている。
安易に勝ち組・負け組という言葉で差別しており、彼らの居場所を狭くしているというのです。
麻生氏は、自分自身を劣等生だと語ります。
実は、中学校時代は145人中140番だったとのこと。
そもそも義務教育に「中学校」は必要なのか?とまで書かれていたので、ニヤリとしまいました。
たしかに、冷静に振り返ると、中学校で教わった知識が社会生活に役立つ場面は多くないように思います。
義務教育にはもちろん良いところもあります。
しかし、一部の人間の選択肢を狭めているのも事実だと感じました。
麻生さんは本の中で、
「従来の画一的な価値観から脱却」と、
「多様な働き方や生き方を許容する社会の必要性」を
繰り返し説いているのが印象的でした。
「高齢化問題」に対する麻生氏の考え方

また、「第三章 高齢化を讃える」では、高齢化社会を悲観的に捉えるのではなく、高齢者の豊富な経験や知識、そして資産を社会全体で活かすべきだと主張しています。
「少子高齢化」を問題とばかり考えるのは、「老人が多い社会はよくない」と言っているも同然であり、この見方に疑問を持たなければならないとしています。
麻生氏の文章が面白いので引用します。
だいたい、すべての大人は子供を経験したことあるけれども老人を経験したことはない。
それなのに勝手に将来が分かりきったような話をするのは僭越だろう。
高齢化を暗黒の未来のように考えることは、実は自分の未来を暗いと考えるのと同じことだ。
そんな馬鹿げた考えは即刻捨てた方が良い。
麻生氏は、こうも語ります。
現実にはご家族やご近所が迷惑しちゃうくらい元気なじいさん、ばあさんがいっぱい。
政界にも元気な老人があふれている。みんなで面倒を見なくてはいけない「弱者」であるはずの老人が、どうしてこんなに多く街を出歩いているのか。
「高齢者」=「弱者」というのも、繰り返し述べているレッテル貼りが原因である。
実は、日本の高齢者の中で、寝たきりとか老人性痴呆などの比率は15%以下。実に85%の老人は元気なのである。
(中略)
加えて、日本の高齢者は世界一お金を持っている。
これまでのように画一的な老人向け政策は改めないといけない。
この考えには完全に同意。
若年層にばかり負担がかかる現在の仕組みは、早く是正して欲しいと強く思いました。
この本は、以下のように続きます。
第四章 「格差感」に騙されてないか
第五章 地方は生き返る
第六章 外交の見取り図
第七章 新たなアジア主義――麻生ドクトリン
特に第四章は、「麻生節」が炸裂。
麻生氏の考え方は、とても興味深く感じました。
ちょっとでも気になった方は、ぜひ本を手に取っていただきたいです。
「とてつもない日本」読書後の感想
この本を読んで、麻生太郎氏のイメージがガラッと変わりました。
麻生さんといえば、スーツとハットをおしゃれに着こなすダンディな政治家。
国会答弁やメディア取材でも、クスッと笑える「麻生節」が印象的です。
この本の中でも、麻生さんらしい表現に何度もニヤリとさせられました。
読書前は「楽観的でマッチョ」な怖いイメージがあったのですが、
読書後は「人情的でバランス感覚のあるリアリスト」に見えてきました。
やはり、編集されたニュースで判断するのではなく、一次情報に触れるのが大事だとつくづく感じます。
他の本や、講演なども見て、麻生さんをもっと知りたいと思いました。
最後に、「とてつもない日本」を読んで意外に思ったことをまとめておきます。
・祖父は、吉田茂だった
・モントリオール五輪に出場したことがある(クレー射撃)
・麻生セメントの社長を務めていた
・高齢者の社会負担増に前向き
・義務教育の見直しも視野にある
・麻生さんがバランス感覚のあるリアリストに見えてきた。
本書「とてつもない日本」が気になる方は、ぜひ手に取ってみてください。
本の目次
第一章 アジアの実践的先駆者
日本は必ずよくなる
成功も失敗も進んでさらけ出す国
安定化装置としての役割
アジアの幸福
第二章 日本の底力
ニートも、捨てたもんじゃない
若者のソフトパワー
日本がロボット大国である理由
私は劣等生だった
第三章 高齢化を讃える
若さは至上か
還暦過ぎたジョン・レノン
老人の労働力
第四章 「格差感」に騙されてないか
平等が生み出す不平等
なんとなく気が晴れないだけ?
教育は格差より悪平等の問題
第五章 地方は生き返る
炭鉱からベンチャーへ
三位一体改革で親離れ
役人の時代の終焉
地方の底力の集合体が日本
第六章 外交の見取り図
外交は難しいか
中国の台頭を喜ぶ
北朝鮮が忘れてはならないこと
靖国は、外交問題ではない
第七章 新たなアジア主義――麻生ドクトリン
SARSと人間の安全保障
価値の外交
民主主義は終わりのないマラソン
自由と繁栄の弧を広げる
国造りのお手伝いをする
中央アジアの「グレート・ゲーム」
自衛官という外交官
アジアとのしなやかなネットワーク
おわりに
関連リンク
麻生太郎オフィシャルサイト:日記「きょうたろう」は必見!
首相官邸ページ:プロフィールに注目。射撃の日本代表としてオリンピックに出場!
自由民主党|歴代総裁ページ:麻生太郎氏の総裁時代が詳しく分かる。